【2026年2月分最新情報】全国の電気料金の値上げについて解説

2026年2月(2025年1月使用分)の電気料金は1月と比べて大きく値下がりします。これは、国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」によって補助金が適用されたためです。
2026年2月の電気料金は値上がりする?
大手電力会社の規制料金プランにおける2026年2月検針分(2026年1月使用分)の電気料金は、1月検針分と比べて大きく値下がりします。これは、国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による補助金(1kWhあたり-4.5円)が適用されたためです。
大手電力会社が提供する「従量電灯」「低圧電力」などの電気料金プラン。料金を決めるのに国の認可が必要とされる。
これらのプランは、電気料金に含まれている燃料費調整額に上限を設けている。そのため、燃料価格が急激に高くなった場合でも、燃料費調整額は一定までしか値上がりせず、電気料金の急激な値上がりを防げる。
一方、規制料金プラン以外の電気料金プランは自由料金プランと呼ばれ、国の認可なしに電力会社が自由に料金を設定できる。これらのプランでは燃料費調整額に上限がないため、燃料価格が高くなれば、その分だけ電気料金も高くなる。ただし、通常時は自由料金プランの方が規制料金プランよりも電気料金が安い傾向にある。
▶規制料金プランとは? 閉じる
以下は、各大手電力会社の規制料金プランの電気料金について、前月と比較したものです。全体で見ると、ファミリー世帯(3~5人程度のご家庭)*におけるひと月の電気代は平均約2,022円値下がりします。
*ひと月あたり450kWh使用と仮定
| 電力会社 | 2026年2月検針分 | 2026年1月検針分 |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 17,095円 (-2,012円) |
19,107円 |
| 東北電力 | 13,821円 (-2,025円) |
15,846円 |
| 東京電力 | 14,052円 (-2,025円) |
16,077円 |
| 中部電力 | 13,175円 (-2,034円) |
15,209円 |
| 北陸電力 | 13,123円 (-2,025円) |
15,148円 |
| 関西電力 | 12,316円 (-2,025円) |
14,341円 |
| 中国電力 | 12,749円 (-2,016円) |
14,765円 |
| 四国電力 | 13,390円 (-2,016円) |
15,406円 |
| 九州電力 | 12,374円 (-2,025円) |
14,399円 |
| 沖縄電力 | 14,277円 (-2,016円) |
16,293円 |
【計算条件】
・目安は3‐5人暮らし。ひと月の電気使用量を450kWh、アンペア制のエリアは契約アンペア数を50Aと想定
・それぞれのエリアの従量電灯プランの基本料金・電力量料金・燃料費調整額・再エネ賦課金の合計
3月も引き続き電気代は安い見込み
なお、補助金は2月使用分にも同額が適用されるため、3月に支払う電気料金も同程度の安さとなる見込みです。
ただし、3月使用分(4月支払い分)からは値引き額が小さくなるため注意しましょう。
| 2026年1~2月使用分 (2026年2~3月検針分) |
4.50円引き /kWh |
| 2026年3月使用分 (2026年4月検針分) |
1.50円引き /kWh |
この補助金によって、ファミリー世帯では3ヶ月で4,725円ほど電気料金が安くなる*ことが想定されます。
*3‐5人暮らしの世帯で、ひと月の電気使用量を450kWhと仮定
これまでの電気料金の推移
これまでの電気料金にどのような変動があったのかを見てみましょう。以下のグラフは、東京電力の過去2年ほどの電気料金の推移を表したものです。
電気料金の推移:ファミリー世帯(3‐5人暮らし)の場合
電気料金(円)
【計算条件】
・東京電力の従量電灯Bを契約していると想定。目安は3‐5人暮らしで、電気使用量が月450kWh、契約アンペア数が50Aと想定
・基本料金・電力量料金・燃料費調整額・再エネ賦課金の合計
・国の電気料金激変緩和措置による値引き単価(2023年2月~9月分は7.00円/kWh、10月~2024年5月分は3.50円/kWh、6月分は1.80円/kWh、9月~10月分は4.00円/kWh、11月分は2.5円/kWh、2025年2~3月分は2.5円/kWh、4月分は1.3円/kWh、2025年7・9月は2.0円/kWh、8月は2.4円/kWh、2026年1~2月は4.5円/kWh、3月は1.5円/kWh)を含む
2024年5月以降の大きな値上がりは、再生可能エネルギー発電促進賦課金の値上がりが主な原因です。
昨年度は1.4円/kWh→3.49円/kWhの大幅な値上げがされたため、電気料金の振れ幅も大きくなっています。
また、2024年8月以降の電気代の変動の主な原因は政府の電気料金に対する補助金に関連しており、単価の変更や制度の停止・再開が影響しています。
2024年からの電気料金の変動の大きな要因である以下の2つについて、詳しく確認しましょう。
電気料金変動要因①再エネ賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)とは、再生可能エネルギーの普及のために電気契約者が等しく負担する税金です。
再エネ賦課金は、電気の使用1kWhにつきいくら、という風に単価が定められています。これを決めるのは経済産業省で、毎年度単価が更新されます。新単価は毎年5月検針分から適用となっています。
2025年度は1kWhあたり3.98円に設定され、制度導入当初から見て最高値となっています。
再エネ賦課金の推移:1kWhあたりの料金
再エネ賦課金単価(円)
上記の値上げに伴って、標準家庭*においては、毎月1,194円の再エネ賦課金の負担が見込まれ、2024年度と比較すると毎月147円分の負担増となります。
*1ヶ月あたりの電力使用量が300kWhの家庭
再エネ賦課金の推移:標準家庭における毎月の負担額
毎月の再エネ賦課金負担額(円)
電気料金変動要因②政府の補助金事業
2022年、ウクライナ侵攻の影響で燃料の取引価格が高騰し、電気料金が急激に値上がりしました。
これに対して政府は2023年1月以降、電気料金の値引きを開始。以来、以下の5つの補助金事業が展開されています。
| 政府による補助金事業 |
|---|
|
| 2023年1月~9月使用分 (2023年2~10月検針分) |
7.00円引き /kWh |
| 2023年10月~2024年4月使用分 (2023年11~2024年5月検針分) |
3.50円引き /kWh |
| 2024年5月使用分 (2024年6月検針分) |
1.80円引き /kWh |
| 2024年8~9月使用分 (2024年9~10月検針分) |
4.00円引き /kWh |
| 2024年10月使用分 (2024年11月検針分) |
2.50円引き /kWh |
| 2025年1~2月使用分 (2025年2~3月検針分) |
2.50円引き /kWh |
| 2025年3月使用分 (2024年4月検針分) |
1.30円引き /kWh |
| 2025年7・9月使用分 (2025年8・10月検針分) |
2.00円引き /kWh |
| 2025年8月使用分 (2025年9月検針分) |
2.40円引き /kWh |
| 2026年1~2月使用分 (2026年2~3月検針分) |
4.50円引き /kWh |
| 2026年3月使用分 (2026年4月検針分) |
1.50円引き /kWh |
▶補助金による値引額を詳しく確認 閉じる
* 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」より。独立系=大手ガス・電力・通信関連会社の子会社でないことを指す
電気料金はどうやって下げればいい?
電気料金をもっと安くしたいと思ったら、「節電」「電力会社の切り替え」をするのがよいでしょう。
節電で電気使用量を減らす
家庭内でとりわけ電気の消費が大きいのは、エアコン・冷蔵庫・照明です。これらの家電の使用方法を見直せば、電気代を効果的に節約することができます。
節電の詳しい方法は以下の記事からご確認ください。
安い電気料金プランを見つけて切り替える
お住まいのエリア、そして電気使用量に応じてもっともお得になる電気料金プランは異なります。
以下の料金比較シミュレーターでは、全国からピックアップした新電力およそ20社の電気料金を比べることができます。
「郵便番号」「1ヶ月あたりの電気使用量」を入力すれば、一番安い電気料金プランがカンタンにわかります。ぜひご活用ください。
電気料金比較シミュレーション
💡世帯人数別:電気使用量の目安(1月分)
・1人暮らし:250kWh /・2人暮らし:440kWh /・3人暮らし:515kWh /・4人暮らし:655kWh
電気料金シミュレーターご利用上のご注意
- 本サービスで表示される料金プランの情報は、各電力会社が公表しているデータを基に作成されています。当該情報について、十分な注意を払った上で定期的に更新を行っておりますが、ご利用時点での料金単価やサービスその他を保証するものではありません。
- 政府による補助金が適用される際、その割引をシミュレーションに反映しています。一部の電力会社では適用外となる場合がございますのでご注意ください。
- シミュレーションには、元々の定額割引が含まれていますが、特典ポイントや一部キャンペーンなどは計算に反映されていません。詳細はシミュレーター内の「特徴」説明や、各電力会社の公式サイトをご確認ください。
- 燃料費調整単価、またそれに相当する電源調達調整単価などは、各電力会社の公表データに基づき毎月更新し、1年分の電気料金に反映しています。現在2026年2月分の単価を基準として計算しています。
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、現在2025年度分の3.98円/kWhを基準に計算しています。
- 自家発電設備や蓄電池の利用による料金の変動は、シミュレーション結果に反映されていません。
- 継続して利用する場合の料金を試算しています。途中解約料や特定の条件で発生する料金は含まれていません。
- 全国どの地域でもご利用いただけます。ただし、離島や集合住宅単位で一括契約されている場合は、料金プランの切り替えができない場合があります。
- 電気とガスを併用している一般のご家庭向けに設計されています。
- ご入力いただいた条件から、当社独自の前提条件に基づいて電力使用量を試算しています。本シミュレーションは参考目安であり、実際の支払額や節約額を保証するものではありません。
- 当社では各料金プランやサービスの詳細についてのご質問にはお答えできません。直接各電力会社にお問い合わせください。
ご利用上のご注意 閉じる
自宅の使用量がわからない?
自分のタイプに合った電力会社がすぐ見つかる!
タイプ別のおすすめ電力会社9選を見る



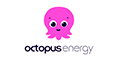




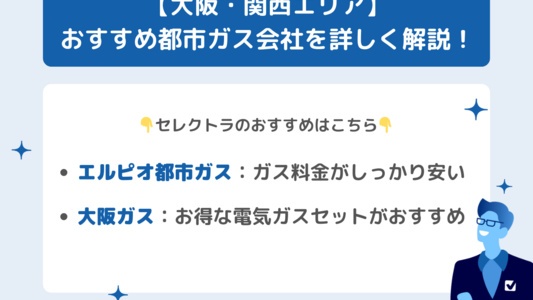
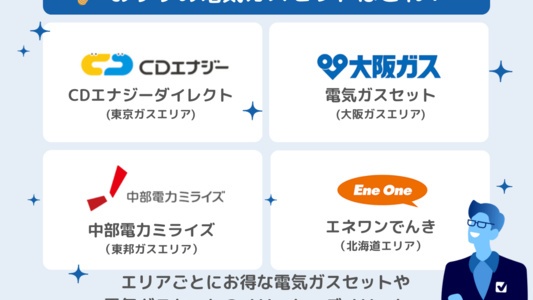
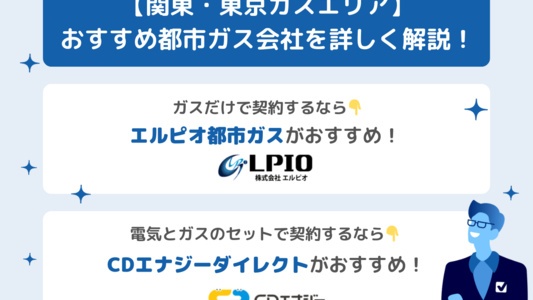
![佐賀県で電気契約におすすめの電力会社💡電気代が安い新電力ランキング・オール電化【[current-date:jp_year_month]最新】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/saga-osusume-2026-1.png.jpeg?itok=ApkIyXsh)
![鹿児島県で電気契約におすすめの電力会社💡電気代が安い新電力ランキング【[current-date:jp_year_month]最新】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/kagoshima-osusume-2026-1.png.jpeg?itok=ZJZCeWhf)