漏電ってどういうこと?漏電について解説

漏電とは、電線やケーブルなどの周りを囲む絶縁(電気を通しにくい物質)が劣化・損傷したりすることによって電気が外部に漏れ出る現象のことです。漏電すると感電・火災などのリスクがあり危険です。電気コードを折り曲げたりしないなどの漏電の予防策を日常的に心がけるようにしましょう。
漏電とは?

漏電しないよう絶縁体が使用される。各芯線が異なる色の絶縁体で、全体が保護用被覆で覆れている3芯の送電ケーブル。
漏電とは、電気が本来通るべきルートをはずれて流れる(漏れる)現象をいいます。
電気は電線・ケーブルなどの電気を通しやすい物質の中を通り流れています。そして、これら電線やケーブルは、外に電気が漏れないようにするために、通常、絶縁(電気を通しにくい物質)で覆われています。
しかしこの絶縁に傷や劣化があったりすると、正常な電気の通り道(電線やケーブルの内)以外にも電気が流れ出てしまうことがあります。このことを漏電と言います。
これが漏電です。漏電すると、感電の危険性がありますし、火災といった深刻な事故の原因となることがあります。
漏電の原因
漏電の原因には以下のようなものがあります。
絶縁の老朽化や損傷
電気配線や電気器具類には通常、電気が漏れないように不導体あるいは各種の部品や装置を利用して電流を遮断する処理(絶縁)がされています。しかし、これが傷ついたり、また、老朽化して被覆がはがれたりすると、外部に電気が流れ出る「漏電」が起こります。
防水機能のない電子機器の浸水
防水性のない電子機器が浸水したり水を浴びたりしても、絶縁機能が衰えて漏電が起こります。
コンセント周りのホコリの蓄積
さらにトラッキング現象という現象にも注意が必要です。
トラッキング現象とは、
- コンセントとプラグのすき間に大量のホコリが蓄積される
- それが湿気を帯びた場合に漏電し、発火する
という現象のこと。
コンセントの部分にすすが付着していた場合はとりわけ要注意です。
その他、漏電の要因としては、
- 電気工事が適切に行われていない
- ネズミなどが電気コードをかじる
- 送電機器への塩分付着により絶縁低下あるいは腐食が起こる
ということも考えられます。
漏電の危険性
漏電は、電力の損失になるだけでなく、感電や火災といった深刻な事故につながる非常に危険な現象です。
以下で具体的なリスクを解説します。
漏電のリスク 感電
感電のリスクに注意が必要です。
体に電流が流れると、痛みやしびれといった障害を受けたり、電流の大きさによっては死に至ることすらあり得ます。特に、10-20mA以上の電流が体内に流れると筋肉が麻痺してしまい、感電箇所から離れられなくなり、長時間電気が流れさらに危険です。
| 1mA | ビリッと感じる。 |
|---|---|
| 5mA | かなり痛みを感じる。 |
| 10mA | 耐えられないほどビリビリする。 |
| 20mA |
筋肉の硬直が激しく、呼吸も困難になる。 麻痺して動けなくなる。 引き続き流れると死に至ることもある。 |
| 50mA | 非常に危険。短時間でも命に危険を及ぼす。 |
| 100mA | 致命的。 |
漏電のリスク 火災

漏電が原因で約1000戸が焼失することになった1955年の新潟大火。
人体は数十ミリアンペアの感電で死に至りますが、この漏電の規模が数百ミリアンペアから数アンペアのレベルに至ると、周囲に火災を引き起こすリスクがあります。
実際、1955年10月には新潟県庁舎第三分館の屋根裏で発生した漏電によって大火が発生しました(「新潟大火」)。日常一般に起こっている火災のなかでも漏電が原因のものは少なくありません。
普段と同じように電気を使っているにも関わらず、電気使用量が異常に増えているようなことがあれば、漏電を疑って早急に対処するようにしましょう。
漏電の予防策
一旦起こると命を落としたり大災害にもなりかねない漏電。一体どのようにして予防策を取ればよいのでしょうか?
以下のような日常のちょっとした心がけで漏電を予防することが可能になります。
- 電気コードを折ったり曲げたり、あるいは束ねた状態で使ったりしない。
- プラグにホコリをためないように定期的に掃除する。
- タコ足線の利用を避ける。
- 濡れた手で電子機器を扱わない。
- 電子機器は湿気の多い所に置かないようにする。
- 定期的に電気配線や電子機器のメンテナンスを行う
- コンセントに感電防止用のカバーを取り付ける(とりわけ幼児のいる家庭)。
しかるべき安全対策と正しい電子機器の使用で、漏電リスクのかなりの部分は回避できると言えるでしょう。漏電を防ぐことは節電にもなりますので、日頃から心がけておきましょう。
\ 電気をお得にしませんか? /



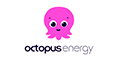

![関東・東京でおすすめの電力会社💡お得な電気・ガスセット・オール電化・一人暮らしのおすすめ【[current-date:jp_year_month]の料金比較ランキング】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/kanto-osusume-202601.png.jpeg?itok=ZuI8_571)
![栃木県の電力会社おすすめランキング💡一人暮らし・ガスセット・オール電化でお得な電気料金プラン【[current-date:jp_year_month]の料金比較】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/tochigi_hero_image.png.jpeg?itok=zvMuO14r)
![神奈川県でおすすめの電力会社💡電気ガスセット・一人暮らし・オール電化【[current-date:jp_year_month]の料金比較】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/kanagawa_hero_image.png.jpeg?itok=b0QHyOH3)
![埼玉県でおすすめの電力会社💡一人暮らし・ガスセット・オール電化【[current-date:jp_year_month]の料金比較】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/saitama_hero_image.png.jpeg?itok=VIcnQqZn)
![千葉県でおすすめの電力会社💡一人暮らし・ガスセット・オール電化が安い電気料金プラン【[current-date:jp_year_month]最新の料金比較】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/chiba_hero_image.png.jpeg?itok=gpNfb09j)
![群馬県人が厳選💡群馬でおすすめの電力会社&電気料金プラン【[current-date:jp_year_month]最新の料金比較】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/gunma_hero_image.png.jpeg?itok=eD4wjoIZ)