1kWh(キロワットアワー)の電気料金はいくら? ‐ 節電にも役立つ知識

全国的には、1kWhあたりの電気代の目安は31円とされています(「公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会」の「新電力料金目安単価」に基づく)。ただし、1kWhあたりの電気代目安は地域や世帯人数によって大きく異なります(▶地域別・世帯人数別の1kWhあたり電気代目安を見る)。
1kWhあたりの電気代を減らしたい方は、信頼度の高いお得な電力会社に切り替えるのをお勧めします。
1kWhあたりの電気代は?
電気代の請求額はkWhという単位で示される電気使用量に応じて決まります。
「kWh」は、電気の使用量を表す単位です。
消費電力(kW)×時間(hour)=kWh数で計算されます。
例:500W(=0.5kW)の電子レンジを30分(0.5h)使用した場合の電気使用量は、0.5kW×0.5h=0.25kWhとなります。
1kWhあたりの電気代はいくらなのでしょうか?全国での目安と地域別の目安を紹介します。
全国での1kWhあたり電気代の目安は?
「公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会」が公表する「新電力料金目安単価」によると、1kWhあたりの料金の目安は31円となっています。
ですから、ざっくりと電気代を計算するには、ご自宅の大体の電気使用量(kWh)×31円で計算すればよいでしょう。
【地域・世帯人数別】1kWhあたりの電気代はいくら?
上記で全国的な電気代目安をお伝えしましたが、実際の1kWhあたりの電気料金については、お住まいの地域や世帯人数によってばらつきがあります。
- 各地域の大手電力会社によって電気料金の設定が異なる
- 世帯人数(⇒電気使用量の多さ)に応じて、1kWhあたりの電気料金の設定が変わる場合がある
というのがその理由です。
そこで、以下では【地域別・世帯人数別】1kWhあたりの電気代目安を示します。
\ お住まいの地域をお選びください /
東京電力エリア(クリックして表示)
| 1kWhあたりの電気代目安 | |
|---|---|
一人暮らし 200kWh/月使用と想定 |
37.1円 / kWh |
2人暮らし 300kwh/月使用と想定 |
37.9円 / kWh |
3‐5人暮らし 450kwh/月使用と想定 |
39.5円 / kWh |
【シミュレーション条件】
・1人世帯=契約アンペア30A、月使用量200kWh/2人世帯=契約アンペア40A、月使用量300kWh/3~5人世帯=契約アンペア50A、月使用量450kWhで想定。
・東京電力の最も一般的なプラン「従量電灯B」を利用と想定。2024年5月時点での単価に基づいて計算。
・1kWhあたりの電気代目安は、基本料金と電力量料金の合計を月使用量で割って算出している。小数点第2位を四捨五入。なお、計算に燃料費調整額・再エネ賦課金を含んでいない。
関西電力エリア(クリックして表示)
| 1kWhあたりの電気代目安 | |
|---|---|
一人暮らし 200kWh/月使用と想定 |
23.5円 / kWh |
2人暮らし 300kwh/月使用と想定 |
24.2円 / kWh |
3‐5人暮らし 450kwh/月使用と想定 |
25.6円 / kWh |
【シミュレーション条件】
・1人世帯=契約アンペア30A、月使用量200kWh/2人世帯=契約アンペア40A、月使用量300kWh/3~5人世帯=契約アンペア50A、月使用量450kWhで想定。
・関西電力の最も一般的なプラン「従量電灯A」を利用と想定。2024年5月時点での単価に基づいて計算。
・1kWhあたりの電気代目安は、基本料金と電力量料金の合計を月使用量で割って算出している。小数点第2位を四捨五入。なお、計算に燃料費調整額・再エネ賦課金を含んでいない。
中部電力エリア(クリックして表示)
| 1kWhあたりの電気代目安 | |
|---|---|
一人暮らし 200kWh/月使用と想定 |
27.8円 / kWh |
2人暮らし 300kwh/月使用と想定 |
28.2円 / kWh |
3‐5人暮らし 450kwh/月使用と想定 |
29.0円 / kWh |
【シミュレーション条件】
・1人世帯=契約アンペア30A、月使用量200kWh/2人世帯=契約アンペア40A、月使用量300kWh/3~5人世帯=契約アンペア50A、月使用量450kWhで想定。
・中部電力の最も一般的なプラン「従量電灯B」を利用と想定。2024年5月時点での単価に基づいて計算。
・1kWhあたりの電気代目安は、基本料金と電力量料金の合計を月使用量で割って算出している。小数点第2位を四捨五入。なお、計算に燃料費調整額・再エネ賦課金を含んでいない。
東北電力エリア(クリックして表示)
| 1kWhあたりの電気代目安 | |
|---|---|
一人暮らし 200kWh/月使用と想定 |
37.9円 / kWh |
2人暮らし 300kwh/月使用と想定 |
38.6円 / kWh |
3‐5人暮らし 450kwh/月使用と想定 |
40.0円 / kWh |
【シミュレーション条件】
・1人世帯=契約アンペア30A、月使用量200kWh/2人世帯=契約アンペア40A、月使用量300kWh/3~5人世帯=契約アンペア50A、月使用量450kWhで想定。
・東北電力の最も一般的なプラン「従量電灯B」を利用と想定。2024年5月時点での単価に基づいて計算。
・1kWhあたりの電気代目安は、基本料金と電力量料金の合計を月使用量で割って算出している。小数点第2位を四捨五入。なお、計算に燃料費調整額・再エネ賦課金を含んでいない。
九州電力エリア(クリックして表示)
| 1kWhあたりの電気代目安 | |
|---|---|
一人暮らし 200kWh/月使用と想定 |
25.4円 / kWh |
2人暮らし 300kwh/月使用と想定 |
25.9円 / kWh |
3‐5人暮らし 450kwh/月使用と想定 |
27.0円 / kWh |
【シミュレーション条件】
・1人世帯=契約アンペア30A、月使用量200kWh/2人世帯=契約アンペア40A、月使用量300kWh/3~5人世帯=契約アンペア50A、月使用量450kWhで想定。
・九州電力の最も一般的なプラン「従量電灯B」を利用と想定。2024年5月時点での単価に基づいて計算。
・1kWhあたりの電気代目安は、基本料金と電力量料金の合計を月使用量で割って算出している。小数点第2位を四捨五入。なお、計算に燃料費調整額・再エネ賦課金を含んでいない。
中国電力エリア(クリックして表示)
| 1kWhあたりの電気代目安 | |
|---|---|
一人暮らし 200kWh/月使用と想定 |
36.8円 / kWh |
2人暮らし 300kwh/月使用と想定 |
37.7円 / kWh |
3‐5人暮らし 450kwh/月使用と想定 |
39.0円 / kWh |
【シミュレーション条件】
・1人世帯=契約アンペア30A、月使用量200kWh/2人世帯=契約アンペア40A、月使用量300kWh/3~5人世帯=契約アンペア50A、月使用量450kWhで想定。
・中国電力の最も一般的なプラン「従量電灯A」を利用と想定。2024年5月時点での単価に基づいて計算。
・1kWhあたりの電気代目安は、基本料金と電力量料金の合計を月使用量で割って算出している。小数点第2位を四捨五入。なお、計算に燃料費調整額・再エネ賦課金を含んでいない。
四国電力エリア(クリックして表示)
| 1kWhあたりの電気代目安 | |
|---|---|
一人暮らし 200kWh/月使用と想定 |
35.0円 / kWh |
2人暮らし 300kwh/月使用と想定 |
35.7円 / kWh |
3‐5人暮らし 450kwh/月使用と想定 |
37.4円 / kWh |
【シミュレーション条件】
・1人世帯=契約アンペア30A、月使用量200kWh/2人世帯=契約アンペア40A、月使用量300kWh/3~5人世帯=契約アンペア50A、月使用量450kWhで想定。
・四国電力の最も一般的なプラン「従量電灯A」を利用と想定。2024年5月時点での単価に基づいて計算。
・1kWhあたりの電気代目安は、基本料金と電力量料金の合計を月使用量で割って算出している。小数点第2位を四捨五入。なお、計算に燃料費調整額・再エネ賦課金を含んでいない。
北海道電力エリア(クリックして表示)
| 1kWhあたりの電気代目安 | |
|---|---|
一人暮らし 200kWh/月使用と想定 |
44.0円 / kWh |
2人暮らし 300kwh/月使用と想定 |
44.7円 / kWh |
3‐5人暮らし 450kwh/月使用と想定 |
45.9円 / kWh |
【シミュレーション条件】
・1人世帯=契約アンペア30A、月使用量200kWh/2人世帯=契約アンペア40A、月使用量300kWh/3~5人世帯=契約アンペア50A、月使用量450kWhで想定。
・北海道電力の最も一般的なプラン「従量電灯B」を利用と想定。2024年5月時点での単価に基づいて計算。
・1kWhあたりの電気代目安は、基本料金と電力量料金の合計を月使用量で割って算出している。小数点第2位を四捨五入。なお、計算に燃料費調整額・再エネ賦課金を含んでいない。
北陸電力エリア(クリックして表示)
| 1kWhあたりの電気代目安 | |
|---|---|
一人暮らし 200kWh/月使用と想定 |
36.9円 / kWh |
2人暮らし 300kwh/月使用と想定 |
37.2円 / kWh |
3‐5人暮らし 450kwh/月使用と想定 |
37.6円 / kWh |
【シミュレーション条件】
・1人世帯=契約アンペア30A、月使用量200kWh/2人世帯=契約アンペア40A、月使用量300kWh/3~5人世帯=契約アンペア50A、月使用量450kWhで想定。
・北陸電力の最も一般的なプラン「従量電灯B」を利用と想定。2024年5月時点での単価に基づいて計算。
・1kWhあたりの電気代目安は、基本料金と電力量料金の合計を月使用量で割って算出している。小数点第2位を四捨五入。なお、計算に燃料費調整額・再エネ賦課金を含んでいない。
世帯人数によって1kWhあたりの電気代が違うのはなぜ?
電力量料金が月々の使用量が増えるほど高くなる価格設定になっているためです。
| 電力量料金単価 | |
|---|---|
| 電力消費量 | 中部電力 従量電灯B |
| 0 - 120 kWh | 21.20 円 / kWh |
| 120 - 300 kWh | 25.67 円 / kWh |
| 300 kWh以上 | 28.62 円 / kWh 割高 |
実際の電気料金には、上記の電力量料金に加えて、毎月一定額が徴収される基本料金(または最低料金)と燃料費調整額・再エネ賦課金が加算されます。
月々最初の120kWhまでは比較的料金が安く設定されていますが、120kWh以上、300kWh以上となるたびに単価が高くなっています。
こうした段階的な料金設定には、電気を多く使えば使うほど電気代が割高になる設計にすることで、国民の節電行動を促す狙いがあります。
1kWhあたりの電気代が安い電力会社は?
それでは、1kWhあたりの電気代が安い電力会社にはどのようなところがあるのでしょうか?当サイトのおすすめ電力会社を紹介します!
- 1kWhあたりの料金がお得になりやすい電力会社
- CDエナジーダイレクト【東京電力エリア】
- idemitsuでんき【沖縄除く全国】
以下で詳しく解説します。
CDエナジーダイレクト【東京電力エリア】

東京電力エリアにお住まいなら、CDエナジーダイレクトの「ベーシックでんき」がおすすめです。
東京電力よりも1kWhあたりの料金が安くなりやすい
東京電力の最も一般的なプラン(従量電灯B)よりも基本料金・電力量料金(第二段階以上)が安く設定されているため、電気代がお得になります。

※ただし、電気の原材料となる燃料の取引価格が極端に高騰した場合は、電気代に含まれる燃料費調整額が東京電力・従量電灯Bよりも高くなり、結果的にお得にならない可能性があります。
実際の料金表(クリックして表示)
| 基本料金 | ||
|---|---|---|
| 契約アンペア数 | 東京電力 従量電灯B 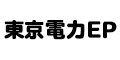 |
CDエナジーダイレクト ベーシックでんきB  |
| 10A | 311.75円 | 276.90円 安い |
| 15A | 467.63円 | 415.35円 安い |
| 20A | 623.50円 | 553.80円 安い |
| 30A | 935.25円 | 830.70円 安い |
| 40A | 1247.00円 | 1107.60円 安い |
| 50A | 1558.75円 | 1384.50円 安い |
| 60A | 1870.50円 | 1661.40円 安い |
| 電力量料金(1kWhあたりの料金) | ||
| 東京電力 従量電灯B |
CDエナジーダイレクト ベーシックでんきB |
|
| 120kWhまで | 29.80円 | 29.90円 |
| 120kWh超えて300kWhまで | 36.40円 | 35.59円 安い |
| 300kWh超える | 40.49円 | 36.50円 安い |
*実際の電気料金には、上記の基本料金と電力量料金の他に、燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金が加算されます。CDエナジーダイレクトの燃料費調整額には上限がないため、燃料価格が高騰している間は東京電力・従量電灯(上限あり)に比べて電気代が高くなる可能性があります。
中部電力×大阪ガスの共同経営なので安心
CDエナジーダイレクトは中部電力と大阪ガスという大手エネルギー会社が共同で経営しているエネルギー企業です。新電力への切り替えに不安を感じておられる方も安心してご利用いただけます。
idemitsuでんき【沖縄除く全国】
ガソリンスタンドでおなじみの出光興産が運営するidemitsuでんきもおすすめです。
120kWh以上の電気料金がお得に
idemitsuでんきの「Sプラン」は、大手電力会社の最も一般的なプラン「従量電灯」と比べて120kWh以上の電気の使用量にかかる料金(電力量料金)が割安になっています。
| 電力量料金(円/kWh) | ||
| 電力使用量 | 東京電力 従量電灯B |
idemitsuでんき Sプラン |
| ~120kWhまで | 29.80円 | 29.80円 |
| 120kWhを超えて300kWhまで | 36.40円 | 34.76円 安い |
| 300kWhを超える | 40.49円 | 37.10円 安い |
・実際の電気料金には、上記以外に基本料金と燃料費調整額および再エネ賦課金が加算・減算される
・東京電力の従量電灯Bは燃料費調整額に上限があるのに対してidemitsuでんきのSプランでは上限がない。仮に燃料価格が高騰した場合、Sプランの燃料費調整額が上限を超えて東京電力よりも電気料金が高くなる場合あり
・再エネ賦課金は電力会社に関わらず一律料金
そのため、毎月120kWh以上電気を使う場合は1kWhあたりの料金が安くなります*。
*ただし、大手電力会社の従量電灯は燃料費調整額に上限があるのに対してidemitsuでんきのSプランでは上限がありません。仮に燃料価格が高騰した場合、Sプランの燃料費調整額が上限を超えて大手電力会社よりも電気料金が高くなる場合があります。

![愛媛県のおすすめ電力会社ランキング💡電気代が安いお得な新電力【[current-date:jp_year_month]最新】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/ehime_hero.png.jpeg?itok=mTFWD5Z0)
![四国電力エリアの安いおすすめ電力会社ランキング💡【[current-date:jp_month]最新の電気料金比較】おすすめオール電化プランもご紹介!](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/shikoku-osusume-202412.png.jpeg?itok=dv3Lr8oL)
![【[current-date:jp_year]最新】和歌山県で電気契約におすすめの電力会社はここ!電気代が安いランキングも掲載](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/wakayama-osusume-202508.png.jpeg?itok=R99WMv67)
![奈良県で電気契約におすすめの電力会社💡一人暮らし・ガスセット・オール電化【[current-date:jp_year_month]の料金比較ランキング】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/nara-osusume-202508.png.jpeg?itok=4IMnff0j)
![滋賀県で電気契約におすすめの電力会社💡一人暮らし・ガスセット・オール電化【[current-date:jp_year_month]の料金比較ランキング】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/shiga-osusume-202508.png.jpeg?itok=1lc5L0NT)
![兵庫県の電力会社:電気&電気ガスセットおすすめランキング💡【[current-date:jp_year_month]最新の料金比較】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/hyogo-osusume-202508_0.png.jpeg?itok=0Ie6G8mu)