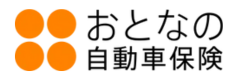ファミリーバイク特約の年間料金は?バイク保険と比べるとどれくらい変わる?
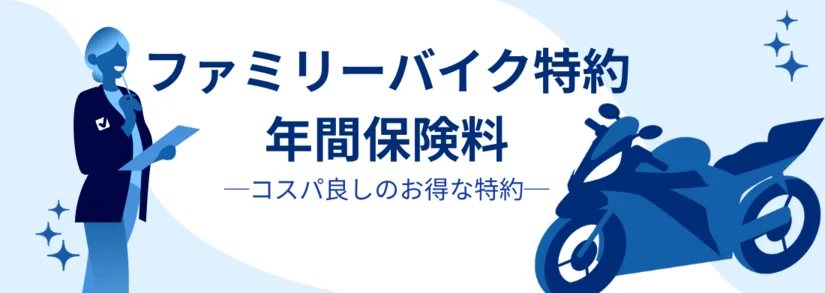
自動車保険に加入していて、さらに125cc以下のバイクに乗る方には便利なファミリーバイク特約。ファミリーバイク特約の年間保険料は約1万円~3万円が相場です。補償の対象者が広く、借りたバイクでも補償できることからコスパの良い自動車保険の特約といえます。
目次:
ファミリーバイク特約の年間保険料はいくら?
| 種類 | 年間保険料の目安 |
|---|---|
| 自損事故型 | 約10,000円 |
| 人身傷害型 | 約30,000円 |
ファミリーバイク特約は、任意保険(自動車保険)のオプションとして加入できるものですので、短期的に見ればバイク保険単体で加入するよりも料金が抑えられます。
ファミリーバイク特約には2つの種類があり、リーズナブルなタイプだと年間約10,000円、補償内容が充実したものだと年間約30,000円くらいの保険料となります。
\ 無料!3分で完了/
自動車保険
一括見積もりへ
ファミリーバイク特約ってなに?
ファミリーバイク特約は、自動車保険に加入している人を対象に、排気量125cc以下の原付バイクなどに乗っている人が安心してバイクに乗ることができるように補償を追加できる特約です。
通常、バイクは強制加入の自賠責保険に加え任意加入のバイク保険に入ることになりますが、原付バイク等は自動車保険とセットにすることで年間の保険料を抑えられます。
徹底比較!自賠責保険 vs バイク保険 vs ファミリーバイク特約
バイクに関係する保険には、強制加入の自賠責保険に加え、今回のメインとなる自動車保険のオプションであるファミリーバイク特約、そしてバイク単体で加入することができるバイク保険があります。
それぞれの保険料の違いや補償範囲の違いなどを確認してみましょう。
| 保険の種類 | 年間保険料 | 対人賠償 | 対物賠償 | 自分のケガ | 自分の車両 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強制加入 | 自賠責保険 | 6,910円 (複数年契約だと安くなる) | 120万円 死亡時3,000万円 後遺障害4,000万円 | × | × | × | |
| 任意加入 | 自動車保険 (ファミリーバイク特約) | 自損型 | 約10,000円 | 最大無制限 | 最大無制限 | ○上限あり | × |
| 人身傷害型 | 約30,000円 | 最大無制限 | 最大無制限 | ○自動車保険の人身傷害に準ずる | × | ||
| 任意加入 | バイク保険 | 約30,000円〜60,000円 ※補償内容による | 最大無制限 | 最大無制限 | ○ | ○ | |
自賠責保険の特徴と料金体系
自賠責保険は、バイクに乗るすべての人が法律で加入を義務付けられている保険です。これに加入していないと、公道を走ることができません。
保険料はバイクの排気量や契約年数によって異なりますが、たとえば125cc以下のバイクを本土(沖縄県・離島を除く)で使用する場合、1年間で6,910円の保険料が必要です。5年分をまとめて契約すると13,310円となり、1年あたり3,000円以下に抑えることも可能です(2025年5月現在の保険料)。
補償内容
- ケガによる治療費:最大120万円
- 死亡時:最大3,000万円
- 後遺障害が残った場合:最大4,000万円
注意すべき点
- 補償されるのは相手の人身損害のみ。物損(車・家屋など)や自分の補償は一切なし。
- 交通事故の場合、健康保険が適用されないため、治療費が全額自己負担(10割負担)となる。
つまり、自賠責保険だけでは補償が不十分なケースが多く、ファミリーバイク特約やバイク保険といった任意保険との組み合わせが必要になります。
ファミリーバイク特約の特徴と料金体系
ファミリーバイク特約は、自動車保険に付帯できるオプションとして加入できる保険です。対象となるのは、主に排気量125cc以下の原付バイクを利用する方で、契約者本人や家族が補償の対象になります。
この特約を利用することで、自賠責保険だけでは不十分な補償をカバーでき、費用を抑えながら安心感を得られます。
年間保険料の目安
- 自損型:年間 約10,000円
- 人身傷害型:年間 約30,000円
自損型は比較的リーズナブルで、単独事故などをカバーする基本的な補償が含まれています。人身傷害型はより手厚い補償内容で、事故相手がいるケースや治療費の実費補償などが含まれています。
補償範囲の特徴
ファミリーバイク特約は、自賠責保険では対応できない相手の車や建物などの物損に対する賠償もカバーします。また、通常の保険では保険を使用すると等級が下がり翌年の保険料が上がってしまいますが、ファミリーバイク特約だけで保険を使った場合は「ノーカウント事故」扱いとなり、等級に影響が出ないのも大きなメリットです。
補償対象となる人とバイク
この特約で補償されるのは、契約者本人だけでなく以下の家族も含まれます:
- 配偶者
- 同居の親族
- 別居の未婚の子
対象者が運転していれば、バイクの所有者や名義は問われず補償されるのが特長です。また、バイクの台数にも制限がないため、家族で複数台所有している場合も1契約でカバー可能です。
バイク保険の特徴と料金体系
バイク保険は、バイク単体で加入できる任意保険です。主に、車を持っていない方やファミリーバイク特約が利用できない方、またバイクを長期間使用する方に向いています。
年間保険料の目安
保険料は補償内容や契約者の年齢によって異なりますが、契約初年度は年間3万円〜6万円程度が相場です。
補償内容の自由度
バイク保険では、自動車保険と同様に補償内容を自由に設計できます。たとえば、以下のような補償を付けることが可能です:
- 対人・対物賠償
- 人身傷害・搭乗者傷害(入通院時の給付金など)
- 車両保険(126cc以上のみ)
- ロードアシスト特約(レッカーサービスなど)
なお、125cc以下の原付には車両保険は付帯できない点には注意が必要です。
等級制度の導入
バイク保険には自動車保険と同様に等級制度があります。無事故で契約を継続すると等級が上がり、保険料が割安になります。
初年度ではファミリーバイク特約の方が安くなるケースが多いですが、長期的にみればバイク保険の方がコストパフォーマンスが良くなる場合もあります。
どの保険に加入するのが良い?
まず大前提として、自賠責保険は法律で定められた強制保険のため、必ず加入しなければなりません。選択の余地があるのは「ファミリーバイク特約」か「バイク保険」かという点です。
選び方のポイント
- 短期間の利用(1年程度)ならファミリーバイク特約の方が安価で手軽。
- 若年層(10〜20代)の場合、バイク保険は年齢によって保険料が高くなる傾向あり。
- 125cc以下のバイクを2台以上保有している家庭では、ファミリーバイク特約が1契約で複数台カバーできるため有利。
- 長期間の利用や125cc超のバイクを所有している場合は、等級が上がることで保険料が割安になるバイク保険の方がコスパが良くなる可能性があります。
ライフスタイルや利用頻度、バイクの排気量や台数、加入者の年齢などによって、どちらが適しているかは異なります。上記のポイントを参考に、自分に合った保険を選びましょう。
ファミリーバイク特約を付けても安い保険会社
具体的にファミリーバイク特約をつけて安い保険会社を知りたいところです。そこでセレクトラは50代で子どもがバイクに乗る可能性のあるご家庭を想定して全10社の保険料を見積もりました。
上述のとおり「自損型」と「人身型」がありますが、自損事故以外で自分のケガも補償される「人身型」でファミリーバイク特約だけでなく、特約を含めた全体の保険料を確認しました。アクサダイレクト・チューリッヒ保険(ネット専用)は「自損型」のみの販売となるためこちらのランキング対象外としています。
関連記事:【2026年最新】50代向け安い自動車保険ランキング
車両保険なし相場:年額63,300円・月額5,670円
車両保険あり相場:年額135,800円・月額12,310円
| 順位 | 車両保険なし 年額・月額保険料 | 車両保険あり 年額・月額保険料 |
|---|---|---|
| 🥇1位 | おとなの自動車保険 49,480円 月払い4,550円 見積もりへ | おとなの自動車保険 105,660円 月払い9,660円 見積もりへ |
| 🥈2位 | 三井ダイレクト 52,390円 月払い4,710円(初回9,420円) 見積もりへ | 楽天損保 118,830円 月払い楽天カード分割 見積もりへ |
| 🥉3位 | SBI損保 56,070円 月払い5,020円 見積もりへ | 三井ダイレクト 119,230円 月払い10,730円(初回21,40円) 見積もりへ |
ファミリーバイク特約をさらに詳しく解説
ファミリーバイク特約では、対象となるバイクの種類や補償される人の範囲に特徴があります。ここではその範囲をわかりやすく紹介します。
補償されるバイクの種類
| 種類 | 補償の可否 |
|---|---|
| 排気量50cc以下の3輪以上の車(ミニカー) | ◯ |
| 排気量125cc以下のバイク | ◯ |
| 排気量126cc以上のバイク | × |
補償の対象となるのは、主に125cc以下の原付・原付二種バイクです。ナンバープレートの色では、ピンク色や黄色のものが該当します。また、排気量50cc以下で3輪以上の車両(ミニカー)も対象です。これらは青色のナンバープレートで分類され、配達用の屋根付きバイクや小型の四輪車などが含まれます。
そして最大の特徴は、補償の台数に制限がないという点です。条件を満たしていれば、複数台の原付バイクを所有していても、1契約で全てを補償対象にすることが可能です。
補償される人の範囲
ファミリーバイク特約では、補償されるのは契約者本人に限りません。以下のような家族も対象になります:
- 契約者本人
- 配偶者
- 同居している親族
- 別居している未婚の子ども
例えば、実家に住む両親や配偶者がバイクを使っている場合や、大学に通う子どもが下宿先で原付を使用している場合も、同じファミリーバイク特約でカバーすることができます。名義が異なるバイクでも、保険対象者が運転していれば補償されるのがポイントです。
補償の範囲
ファミリーバイク特約では、以下の4つのリスクに対して補償が用意されています。
| リスク | 保険の種類 | 補償内容 |
|---|---|---|
| 相手のケガなど | 対人賠償保険 | 任意保険と同様の補償 |
| 相手の車両や財物 | 対物賠償保険 | 任意保険と同様の補償 |
| 自分自身のケガなど | 人身傷害保険、搭乗者傷害保険 | 補償タイプによる |
| 自分のバイクや物損 | 車両保険 | 補償されない |
ポイント:
自分のバイクの損傷に対しては補償されません。これはバイク保険でも125cc以下の場合は同様です。
自損型と人身傷害型の違い
ファミリーバイク特約には「自損型」と「人身傷害型」の2種類があり、補償範囲が大きく異なります。
| 事故の状況 | 自損型 | 人身傷害型 |
|---|---|---|
| 単独事故・相手に過失がない場合 | ◯ 補償あり | ◯ 補償あり |
| 相手がいて過失がある事故 | × 補償なし | ◯ 補償あり |
支払われる保険金の例
| 補償項目 | 自損型 | 人身傷害型 |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 1,500万円 | 任意保険と同額 |
| 入院日額 | 6,000円 | 任意保険と同額 |
| 通院日額 | 4,000円 | 任意保険と同額 |
補償選択時の注意点
- 人身傷害型を選べない保険会社もあるため、契約前に必ず確認しましょう。
- 保険料だけで比較しないのが鉄則。補償範囲が広い人身傷害型は保険料が高めですが、安心感は大きくなります。
同じ「ファミリーバイク特約」という名称でも、実際には内容が異なることがあるため、契約前には自損型か人身傷害型か、しっかり確認することが大切です。
ファミリーバイク特約で知っておきたい4つの疑問
ファミリーバイク特約は125cc以下の原付バイクに乗る方にとってコスパの良い保険ですが、いくつか注意点もあります。ここではよくある5つの疑問とその答えを解説します。
1. 補償されないケースは?
- 原付バイクには車両保険が付帯されないため、壊れても修理費は自己負担
- 自動車保険に付帯していてもロードサービスは利用不可
- 排気量126cc以上のバイクに乗って事故を起こした場合は補償対象外
つまり、ファミリーバイク特約はあくまで原付専用の補償です。対象外の排気量やサービスに関しては別の保険を検討する必要があります。
2. 二人乗り中の事故は補償される?
結論として、誰を乗せていたかとどの特約を選んでいるかが鍵です。たとえば:
| 事故の相手 | 自損型 | 人身傷害型 |
|---|---|---|
| 家族 | × 補償されない | ◯ 補償される |
| 他人(友人など) | ◯ 補償される | ◯ 補償される |
家族を乗せていた場合は「人身傷害型」の特約に入っていないと補償されないので、特約の種類は非常に重要です。
3. 友人のバイクでも使える?
ファミリーバイク特約はバイクに対してではなく人にかかる保険です。補償対象者が運転していれば、バイクが他人のものであっても補償の対象になります(125cc以下に限る)。
4. 保険を使ったら翌年の保険料は上がる?
ファミリーバイク特約はノーカウント事故扱いです。つまり、特約を使っても等級が下がることはなく、翌年の保険料にも影響がありません。バイク保険との大きな違いのひとつです。
ファミリーバイク特約のメリットとデメリット
これまで紹介してきた内容をもとに、ファミリーバイク特約のメリットとデメリットを一覧で整理します。
| メリット | デメリット |
他人のバイクでも・何台でも補償される | ロードサービスが使えない |
年齢・使用用途が制限されない | 搭乗者傷害保険が付帯できない |
保険金を受け取ってもノーカウント(等級に影響なし) | 等級による保険料の割引がない |
短期的な保険料は割安 | 長期契約では任意バイク保険より割高になることも |
ファミリーバイク特約の申し込み方法
原付バイクを購入した場合や、家族が新たに原付を使い始めた場合は、ファミリーバイク特約への加入を検討しましょう。加入には以下のような手続きがあります。
1. 自動車保険申し込みと同時に加入
ファミリーバイク特約は、自動車保険のオプションとして加入するのが基本です。保険の契約期間中に追加するには、契約の見直しや再契約が必要になる場合があります。
2. 契約期間中でも追加できる場合も
保険会社によっては契約期間の途中でもファミリーバイク特約を追加できるケースがあります。保険代理店やインターネットのマイページ、コールセンターに問い合わせて確認しましょう。
3. 中途解約+新規契約も選択肢
途中追加ができない場合、現在の契約を解約して新たに特約付きの契約を結ぶ方法もあります。等級が高くない場合(または新規契約直後)なら、大きなデメリットにはなりません。
ファミリーバイク特約はこんな方におすすめ
最後に、ファミリーバイク特約が特に向いている利用者のケースを紹介します。
- 20歳以下の未婚の子どもがいて、原付を使っている
- 家族の中で複数人が原付に乗る可能性がある
- 他人から原付を借りて乗ることがある
- 原付の利用が一時的(在学中など)で済む見込みがある
例:50歳のあなたが自動車保険に加入している場合で、
- 大学寮で原付通学する18歳の娘(別居)
- 週に数回ミニバイクに乗る75歳の父(同居)
このような場合、あなたのファミリーバイク特約により、2人とも補償対象になります。家族全体を手軽にカバーできるという点で、非常に有効な保険と言えるでしょう。