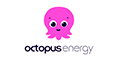脱炭素社会に向けた日本の取り組み

地球温暖化の防止が喫緊の課題となっている今、世界中で脱炭素社会に向けた動きが活発になっています。日本も「2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする」という目標をかかげています。日本が脱炭素社会に向けてどのような取り組みを行うのかについて調べてみました。
スタートは出遅れ
菅義偉首相は2020年10月、国会で就任後初めての所信表明演説をしました。この中で、首相は「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする。ここに宣言する」と述べ、日本でも脱炭素社会への取り組みが本格的に動き始めました。
それまでの「50年までに80%削減」という目標をさらに進めたわけですが、世界ではすでに約120か国が同じ目標を掲げています。イギリスやフランス、スウェーデンなどは「実質ゼロ」を法制化して取り組み始めているのに対し、主要国で日本とアメリカだけが「50年実質ゼロ」を表明していませんでした。日本は世界の大勢から取り残され、大きく出遅れてスタートラインに立ったというわけです。
なぜ「脱炭素」が必要?
では、なぜ多くの国が「50年実質ゼロ」を目標にしているのでしょう。背景には、2015年に合意されたパリ協定があります。地球温暖化による災害や異常気象などが相次ぐ中、各国が取り決めた温暖化対策の国際的なルールです。
パリ協定は、世界の平均気温上昇を産業革命以前より2度以内に抑える、21世紀後半には温室効果ガス排出量と森林などによる吸収量のバランスをとることが目標です。日本を含め約160か国が参加し、各国が「50年実質ゼロ」を目標に掲げるようになりました。
トランプ前大統領が離脱を決めたアメリカもバイデン大統領に代わってパリ協定に復帰し、世界最大の排出国中国は2060年を目標にしています。温室効果ガスの削減という共通の目的に向かって各国が取り組みを始める中、日本も目標達成を迫られる状況にあります。
CO2を減らすために、私たちにできることは? 電力自由化以降、私たちは電力会社を自由に選べるようになりました。再エネを多く使った電気料金プランに電気を切り替えることによって、日常生活で排出するCO2を減らすことができます。
再エネを使った電気料金プランを見る
日本の脱炭素社会に向けた主な取り組み
日本は「50年実質ゼロ」の目標をどう実現するのでしょうか。
菅首相の宣言を受け、政府は2020年12月に「グリーン成長戦略」を発表しました。洋上風力産業、自動車・蓄電池産業、資源循環関連産業など14の重要分野の技術革新を予算や税制、規制改革などで後押しし、温暖化対策と経済成長の両方を実現するとしています。
これら14の分野は、以下のように「エネルギー関連産業」「輸送・製造関連産業」「家庭・オフィス関連産業」の3つのに大きく分けられます。いくつかの取り組みについて見てみましょう。
| エネルギー関連産業 |
|---|
| 洋上風力産業 燃料アンモニア産業 水素産業 原子力産業 |
| 輸送・製造関連産業 |
| 自動車・蓄電池産業 半導体・情報通信産業 船舶産業 物流・人流・ 土木インフラ産業 食料・農林水産業 航空機産業 カーボンリサイクル産業 |
| 家庭・オフィス関連産業 |
| 住宅・建築物産業/ 次世代型太陽光産業 資源循環関連産業 ライフスタイル関連産業 |
エネルギー関連産業
国内から出るCO2の約4割は発電によるものといわれ、発電に伴うCO2排出を減らす必要があります。成長戦略では太陽光、風力などの再生可能エネルギー(再エネ)を最大限導入するとし、2050年の発電量全体に占める再エネ割合の目標を今の約20%から50~60%に引き上げています。今の発電の約7割を占める天然ガス、石炭、石油などの火力発電の代わりに、原子力とCO2回収を前提にした火力30~40%、水素とアンモニア発電を10%程度と見込んでいます。
この実現に向けて、エネルギー関連産業では、洋上風力、燃料アンモニア、水素、原子力の4つの産業を重要分野に挙げています。アンモニアや水素はCO2を出さない発電の燃料などとして注目され、原子力は小型の原発開発などが期待されていますが、いずれもまだ実用化のめどは立っていません。
この中で、最も現実的なのが洋上風力産業です。遠浅の海が広がるヨーロッパでは、世界の4分の3を占めるといわれるほど洋上風力発電が盛んです。日本周辺には適地が少なく、建設コストが高いことなどで建設が遅れていましたが、千葉、秋田、長崎県沖の促進区域から利用が本格化しそうです。成長戦略では2040年には洋上風力で3000万~4500万キロワットの発電を見込んでいて、利用が進めば発電コストが下がり、発電機や風車の羽(ブレード)などを供給する関連産業が育つ可能性もあります。
輸送・製造関連産業
重要分野には自動車・蓄電池や半導体・情報通信、食料・農林水産など7つの産業が挙げられています。
中でも、私たちに最も身近なのは自動車かもしれません。日本の自動車メーカーは1990年代からエンジンとモーターを併用してCO2排出量を減らすハイブリッド(HV)車の開発に力を入れてきました。その結果、今では新車販売の3割以上をHV車が占め、数%の欧米を大きくリードして普及が進みました。
しかし、HV車とはいっても走行中はCO2が排出されます。パリ協定を受け、欧米や中国では2025~40年にかけてガソリン車、ディーゼル車のほか、さらに進んでHV車の新車販売も禁止する動きが出始めています。日本政府も「遅くとも2030年代半ばまでに乗用車の新車販売で電動車を100%にする」と表明しています。日本の場合「電動車」には電気自動車(EV)だけでなくHV車も含まれますが、日本ではEVは乗用車全体の1%にも満たないほど普及が遅れています。EVの普及には走行距離を伸ばす蓄電池の開発や急速充電ができるスポットの増加など多くの課題があり、さらに進んだ燃料電池車の普及も期待されています。
家庭・オフィス関連産業
重要分野は住宅・建築物/次世代型太陽光、資源循環関連、ライフスタイル関連の3つの産業です。
住宅・建築物では、再生可能でCO2を固定する木材を高層建築などでもさらに利用していくこと、エネルギー変換効率の高い次世代型太陽電池の開発などが期待されています。プラスチック製品の再生可能素材への代替、リサイクル技術の一層の開発などもさらに進める必要があります。
今後の課題は?
ヨーロッパでは2020年、発電量に占める割合で再エネ(38%)が化石燃料(37%)を初めて上回りました。風力や太陽光発電が増えたのが要因で、ヨーロッパでは日本でも導入されている電気の固定価格買取制度(FIT制度)が再エネの普及を後押ししてきました。しかし、再エネ電気を割高な固定価格で買い取る費用は電気料金に上乗せされ、消費者が負担することになります。再エネの導入が盛んなドイツの一般家庭の電気料金が1キロワット時あたり約38円かかるのに対し、原発が7割近くを占めるフランスでは約24円にとどまります。再エネのコストを下げる技術革新が求められています。
鉄鋼やセメントなどの素材業界をはじめ、石炭や石油などのエネルギーが大量に必要でCO2削減への対応が難しい業界もあります。水素やアンモニアなどに代替したり、排出したCO2を地中に封じ込めたりする新技術も検討されていますが、技術的な難しさやコストが高いなどの課題があります。温暖化対策にいかに対応し、国際競争力を維持していくか、様々な産業分野で難しい対応が迫られています。
まとめ
2020年10月、菅義偉首相が「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」と宣言し、日本でも脱炭素社会への取り組みが本格化してきました。しかし、すでに120か国以上が同じ目標を掲げて取り組んでいて、日本は大きく出遅れてスタートラインに立った形です。
菅首相の宣言を受けて、国は「グリーン成長戦略」をまとめました。洋上風力産業、自動車・蓄電池産業、資源循環関連産業など14の重要分野を挙げ、技術革新を後押しすることで、温暖化対策と経済成長の両方を実現するのが目的です。
エネルギー関連産業では、洋上風力、燃料アンモニア、水素、原子力の4つの産業を重要分野に挙げています。太陽光、風力などの再生可能エネルギー(再エネ)を最大限導入し、2050年の発電量全体に占める再エネの割合を今の約20%から50~60%に引き上げるとしています。他に原子力とCO2回収を前提にした火力30~40%、水素とアンモニア発電を10%程度と見込んでいます。アンモニアや水素はCO2を出さない発電の燃料などとして注目され、原子力は小型の原発開発などが期待されていますが、いずれもまだ実用化のめどは立っていません。
この中で、最も現実的なのが洋上風力産業です。ヨーロッパではよく目にする洋上風力発電ですが、日本周辺では建設コストが高いことなどで導入が遅れていました。国は2020年に千葉、秋田、長崎県沖の促進区域を指定し、今後利用が本格化しそうです。成長戦略では2040年の洋上風力の発電量を3000万~4500万キロワットと見込んでいます。導入が進めば発電コストが下がり、発電機や風車の羽(ブレード)などを供給する関連産業が育つ好循環が期待できます。
輸送・製造関連産業は自動車・蓄電池、半導体・情報通信、食料・農林水産など7分野です。中でも、私たちに最も身近なのは自動車かもしれません。パリ協定を受け、欧米や中国では2025~40年にかけてガソリン車、ディーゼル車のほか、さらに進んでHV車の新車販売も禁止する動きが出始めています。日本政府も「遅くとも2030年代半ばまでに乗用車の新車販売で電動車を100%にする」と表明していますが、日本ではEVは乗用車全体の1%にも満たないほど普及が遅れています。EVの普及には走行距離を伸ばす蓄電池の開発や急速充電ができるスポットの増加などが必要で、さらに進んだ燃料電池車の普及も期待されています。
家庭・オフィス関連産業は、住宅・建築物/次世代型太陽光、資源循環関連、ライフスタイル関連の3つの産業を重要分野にしています。住宅・建築物では、再生可能でCO2を固定する木材を高層建築などでもさらに利用していくこと、エネルギー変換効率の高い次世代型太陽電池の開発などが期待されています。資源循環関連ではプラスチック製品の再生可能素材への代替、リサイクル技術の一層の開発などもさらに進める必要があります。