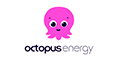電源構成とは? 電源構成で電気料金を選ぶのは意味がある?

電源構成とは一体何でしょう。電源構成について、また今後の課題について調べてみました。また、電気料金プランを選ぶときに電源構成で選ぶことは意味があるのかも考察してみました。
- 電源構成を見れば、その電気が作られた方法(火力、原子力、太陽光、風力など)とその割合がわかります。
- 現在、日本の電源構成は火力発電が約9割ですが、ベストミックスのために再エネおよび原子力発電の拡大が政府目標となっています。
電源構成とは?
電源構成という言葉を聞いた事はありますか?エネルギーミックス、あるいはエネルギーのベストミックスという言葉だったら聞いたことがあるという方もいるかもしれません。

電源構成はエネルギーミックスと同義語で、電気が作られる方法の割合を示しています。
「電源構成」と聞くとなんとなく難しい言葉のようですが、私たちが電気を安定して使用するために関係のあることです。解説していきます。
例えば、現在日本の電力の多くは火力発電(石炭火力発電・石油火力発電)に頼っています。そのため、電気代は火力発電の燃料となる石炭・石油・液化天然ガスの価格に左右されます。
また仮に原子力発電だけに頼った場合、事故が起こると一気に電気が供給できなくなります。(さらにもし事故が起こったら、その処理もとてつもなく大変です。)
では再生可能エネルギーはどうでしょう?太陽光発電や風力発電だけで電気を賄おうと思っても、このような発電は天候に左右されるため、発電の安定性という点で問題があります。例えば太陽発電をとっても夜は発電ができませんね。
つまりどの発電方法にも弱点があり、パーフェクトではありません。言い換えれば、1つの発電方法だけに頼るのはリスクが高い=電気の安定供給が保証できない、ということになります。
電力会社が電気を安定して供給し続けるためには、ひとつだけのエネルギー源に頼らず、それぞれのエネルギーの特徴を活かして、バランスよく組み合わせていくことが不可欠なのです。
発電の種類とその割合を示したものが「電源構成」というわけです。
電気代平均6%削減、最短5分で最適プランが見つかる「セレクトラのらくらく窓口」

セレクトラのらくらく窓口は、お客様に最適な電力・ガス料金プラン探しを無料でサポートします。
セレクトラのらくらく窓口
4.7/ 5
(ご利用者様の声はこちら)

電気代平均6%削減、最短5分で最適プランが見つかる「セレクトラのらくらく窓口」
セレクトラのらくらく窓口までご相談ください。お客様に最適な電力・ガス料金プラン探しを無料でサポートします。
セレクトラのらくらく窓口: 4.7/ 5 (ご利用者様の声はこちら)

電源構成 - 発電方法の種類と特徴
日本には、水力、石油火力、石炭火力、LNG(液化天然ガス)、原子力、そして太陽光発電や風力発電や地熱発電等の再生可能エネルギーといった様々なエネルギー源を活用した発電設備があります。
それぞれの発電方法には、燃料・資源調達の安定性、稼働・運用特性、環境負荷、経済性(設備費用や燃料費)などの特性がありますので、見ていきましょう。
| 地熱発電 |
|
|---|---|
| 水力発電 |
|
| 原子力発電 |
|
| 石炭 (火力発電) |
|
| LNG (火力発電) |
|
| 揚水式水力 |
|
| 太陽光発電 |
|
| 風力発電 |
|
これらの特性を考えたた上で、できるだけ安価に、かつ安定的に電力を供給できるよう、どのように電源構成のバランスをとっていくかが重要な課題なのです。
ベース電源、ミドル電源、ピーク電源
どのように電源構成のバランスをとっていくのか、という時に重要なのが、ベース電源、ミドル電源、ピーク電源、という電源を3つに分ける考え方です。
電力はためておくことが出来ないため、常に需要と供給を一致させていかなければなりません。しかも電力需要は季節や曜日、時間帯によって常に変化しているため、発電量をこの変化にいかに合わせていくかがとても重要になります。
そこでこのような電力需要に対応するべく編み出されたのが、ベース電源、ミドル電源、ピーク電源という3つの電源の組み合わせによる電源構成です。
ベース電源

ベース電源は、安定的に発電することができ、昼夜を問わず継続的に稼働できる電源のことです。
基幹の電源のため、コストが安い事も求められます。東日本大震災以前は、水力発電所や原子力発電がベース電源を担ってきました。
震災後は原発の多くが停止しているため、現在は大規模な火力発電所がこのベース電源の代わりを果たしています。
とはいえ、火力発電は発電コストに占める燃料費の割合が高い上、発電時のCO2排出問題も抱えているため、長期的にベース電源の役割を果たすのは難しいと考えられています。
ミドル電源
ミドル電源とは、ベース電源とピーク電源の中間的役割を果たす電源です。
震災前までは主として火力発電所がこのミドル電源の役目を果たしてきました。
経済産業省は、発電コストがベース電源の次に安く、電力需要の動向に応じて、出力を機動的に調整できる電源とミドル電源を定義しています。
ピーク電源
ピーク電源は、1日のうち需要が大きな時間帯だけを受け持つ電源です。
発電コストは割高であるものの、電力需要の変動に応じて出力を調整出来る発電施設が、このピーク電源の役目を果たしています。主に揚水式水力発電所や、小規模でボイラ出力の増減が容易な火力発電所などです。
電源のベストミックスとは、ベース電源とピーク電源、ミドル電源のそれぞれの特性を発揮させながら、最大のシナジー効果を発揮できるようにそれぞれの電源を調整することです。しかし上記のように、ベース電源となりうる電源の確保から環境負荷に関する課題まで、様々な課題を抱えています。

電気代平均6%削減、最短5分で最適プランが見つかる「セレクトラのらくらく窓口」

セレクトラのらくらく窓口は、お客様に最適な電力・ガス料金プラン探しを無料でサポートします。
セレクトラのらくらく窓口
4.7/ 5
(ご利用者様の声はこちら)

電気代平均6%削減、最短5分で最適プランが見つかる「セレクトラのらくらく窓口」
セレクトラのらくらく窓口までご相談ください。お客様に最適な電力・ガス料金プラン探しを無料でサポートします。
セレクトラのらくらく窓口: 4.7/ 5 (ご利用者様の声はこちら)

日本の電源構成の推移
日本のエネルギー自給率は、5〜6%と極めて低いです。国内に天然資源が乏しく、かつ産業が発達しているので消費は多いのが理由です。
そのため、日本ではエネルギー源の調達を恒常的に輸入に頼らざるを得ない状況で、それはつまり、常に世界情勢や市場の動きの影響を受けやすいという事です。
これまでにも2度のオイルショック、湾岸戦争などによってエネルギー危機が起こりました。
そのため、石油への依存度を減らす努力が行われたり、東日本大震災後は原子力発電停止により、原子力に変わる電源として液化天然ガス(LNG)への依存が急増したりと、様々な変遷をたどってきました。
第1次石油危機および湾岸戦争時
これまでの日本の電源構成の推移をみると、1973年の第一次オイルショック時までは石油依存度が71.3%と極めて高く、次に水力発電(17.2%)、石炭火力発電(4.6%)と続き、原子力発電(2.6%)やLNG(2.4%)などはごく僅かであったことが分かります。1991年の湾岸戦争時にはこれから一転して、原子力発電が27.8%、LNGが23.1%と急増し、反対に石油依存度が1973年の71.3%から24.5%にまで下がり、原子力発電ととLNG火力発電、石油が主要エネルギー源をほぼ3等分した形となっていました。

(資源エネルギー庁の資料より転載)
東日本大震災以前と以後
原子力は1980年代以降、徐々に日本のエネルギー源としてのシェアを増やし、ほぼ3割近くを担うようになっていました。しかし、2011年の東日本大震災後、安全性がおおいに問われることになり、ほとんどの原子力発電所は稼働停止しています。このため、原子力の代替発電燃料としてLNGや石油をはじめとする化石燃料の輸入が急増。原燃料費のコスト増によって電気料金値上げに踏み切った電力会社は少なくありません。

(資源エネルギー庁の資料より転載)
震災から年数を経た事で、原子力発電所は徐々に稼働再開しています。
ただ、大きな事故に繋がる原子力発電所は特に地元の反対が強く、今後どれくらいの割合を原子力に依存していくかが議論されています。
最適化に向けての今後の電源構成の目標
今後のエネルギー政策として、経済産業省は2015年6月1日、「2030年度の望ましい電源構成(ベストミックス)」案を発表しました。この中で以下のような目標水準を掲げています。
- 原子力を含む一次エネルギーの自給率を約25%とすること。
- 電力コストを現状より引き下げること。
- 欧米に比べて遜色のない温室効果ガス削減目標を達成すること。
その上で2030年の望ましい電源構成として、原子力20%、再生可能エネルギー24%、LNG火力27%、石炭火力26%、石油火力3%といった比率を想定しています。
ちなみに2013年度の電源構成と比較すると以下のようになります。
| 電源 | 原子力 | LNG火力 | 石炭火力 | 石油火力 | 再エネ(括弧内は水力) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 1% | 43% | 30% | 14% | 11%(8.5%) |
| 2030年 | 20%程度 | 27%程度 | 26%程度 | 3%程度 | 24%(9.2%)程度 |
このように、経済産業省案では原子力を震災前より少し低めに設定しながらも再導入するとともに、再生可能エネルギーを大幅に増やしたい意向です。
その内訳は水力8.8〜9.2%、太陽光7.0%、バイオマス3.7〜4.6%、風力1.7%、地熱1.0〜1.1%と想定されています。
太陽光の比重が現在よりも非常に高まっていることが特徴です。
この2030年の望ましい電源構成についての是非や実現制に関しては、今後ともさまざまな議論がなされていくものと考えられます。
電源構成の開示
経済産業省はまた、電源構成の理想を発表する一方で、2016年4月の電気の小売り全面自由化後に電気を販売する事業者に対して、電源構成の開示を求めています。
これは、再生可能エネルギーから原子力まで、電源の特性を利用者に分かりやすく伝えることで、自由化後の電力会社を選ぶ際の判断材料にしてもらうことを狙ったものです。

電源構成は国全体の電力だけでなく、各電力会社の電気についても重要です。
ただし、結局、小規模な電力小売事業者にとっては情報開示が負担になること、一般家庭を中心に原子力による電力の購入を望まない層が少なくないことなどを理由に、「電源構成の開示は望ましい」にとどめて開示するかどうかは各電力会社の判断に委ねられることになりました。
電力・ガス取引等監視委員会が2016年5月25日に発表した「電源構成等の開示状況」によると、「一般家庭への供給を既に行っている事業者」96件のうち25件が「電源構成の開示及びCO2排出係数」の開示を行っているというのが現状です。
義務化されていない電源構成の開示ですが、電力自由化によって自然エネルギー(Fit電気、再生可能エネルギー)の比率が高い電力会社が増加傾向にあります。
再生可能エネルギーの利用などを消費者にアピールしたい電力会社は積極的に電源構成を開示しています。また、大手電力会社10社は、いずれも電源構成を開示しています。
電源構成で電気料金プランを選ぶことは意味があるの?
電源構成の開示は義務ではないため、電源構成を開示している電力会社としていない会社があることをご説明しました。
それでは電源構成の内容で電力会社(電気料金プラン)を選ぶことは意味があるのでしょうか?
電気は様々な発電所で作られた電気がいったんひとつにまとめられてから契約者のもとに届けられます。この段階で発電方法が違う電気が一つに混ざり合うため、たとえ電源構成で電力会社を選んでも、そのままの電源構成で契約者のもとに電気が届けられるわけではありません。
例えば「うちでは絶対に再エネしか使いたくない」と思っていても、電気が届く前の過程で、自宅に届く電気の中に再エネ以外の電気が混ざってしまうのを避けることはできません。しかし、再エネを使っている電力会社を選んで市場への意思表示をすることは、再エネの発電量を増やすための一歩となるでしょう。
したがって、自分の好きな電源だけを選んで家に届けてもらうことはできませんが、電源構成を選ぶことには意味があると言えます。
電源構成のまとめ
このように、電源構成とは電気が作られる方法の割合を示しており、電源のベストミックスとは、ベース電源とピーク電源、ミドル電源のそれぞれの特性を発揮させながら、最大の効果を発揮できるようにそれぞれの電源を調整することです。
地球温暖化など環境問題が深刻化するなか、これからの電源のベストミックスは、電力の安定供給のための電源を確保しながら、いかに環境負荷を減らして行くかといった問題もあります。
経済産業省は、2030年度の望ましい電源構成(ベストミックス)」案として、水力発電8.8〜9.2%、太陽光発電7.0%、バイオマス発電3.7〜4.6%、風力発電1.7%、地熱発電1.0〜1.1%、を目標水準として出しました。
震災後の電力不足や原子力のリスクを経験したこと、また電力小売りの自由化により、国民の関心もこれまで以上に高まっています。
そんな中、いかにエネルギー源を確保し、環境問題にも寄与しながら、電力の安定供給を維持していくかが、これまで以上に重要な課題となっています。